「コンサルいれたんだけど、いまいち上手く回らないんだよな~」
とか
「言ってることが正しいのは分かるんだけどそうじゃねぇんだよな~」
とかとか。
何かを指導した/された経験のある人は触れたことのあるであろうこれらのフレーズ。
なんでこんなことになっちゃうんだろうねぇ・・・
「as is」と「to be」と「can be」
いわゆる『現状どうなっているか?』と『将来どうなっているべきか?』と『どこまでならできるか?』みたいな状況を説明するのにつかわれる言葉たち。
それぞれ『いまやっていること』『理想像』『実現可能な落としどころ』みたいな表現です。
でもまあ・・・こ~れがやっかい。
『as is』と『to be』はいいんですよ。現状の客観視と将来像の設定なので。現状の誤認さえしてなければ。
問題は『can be』
字面だけみれば『能力的にどの程度ならできるか??』に論点を設定したくなります。。
リードする側とされる側の一番の違い
そうやって課題設定する側は大抵「やる気に満ち溢れた人たち」です。
『できるんだからやりきるんだ!!』の人たちですね。
自分もどちらかといえばそっち側なので気を付けたいところなんですが・・・
やりたくねぇもんはやらねぇよ!!
ってのが実際のとこだと思います。
理屈上正しいことを言われてるのは分かるけど・・・
- 定常業務にプラスして実行するリソースがない
- チームの業務フローの再整備が発生
- 業務フローの変化による人員の再編成
などなど移行期の負荷が爆増します。。
それに対して得られる報酬は??
労働時間の短縮?
より高度な仕事への集中??
運が良ければ一部の人がなんらかのポジションにつけるかもね???
それを望む人、望まない人で課題への取り組み具合に差が出そうですね。。
『can be』じゃなくて『want to be』
結局のところ実行可能範囲っていうのは
『能力的にどこまでならできるか?』
ではなく
『どこまでならやる情熱があるか?』
に依存すると思っています。
ダイエットとか禁酒/禁煙みたいなもんっすね。
提案者が健康診断に引っかかってそうなら
「努力次第で改善できますよ?なんで実行しないんですか?? 笑」
くらい言っちゃっていいと思います。
だって今あなた同様のことを人に対してやってますよねぇ?って。
人間の行動原理、行動基準はそんなに機械的じゃないよ
『客観的事実をもとに論理的整合性のある課題設定を行う』
てのが従来推奨されてきた指導方針だったと思います。
が、そんなんだから「AIに取って代わられる」とか言われるんですね。実際それってAIの得意分野だし。
どんな提案も実行するのはそれに従事する『人間』です。
人間は『合理性と感情』で動く生き物です。
感情という要素を汲み取る、それができない事業企画者なりコンサルなりは淘汰されていくんじゃないでしょうか?
ほな、また!

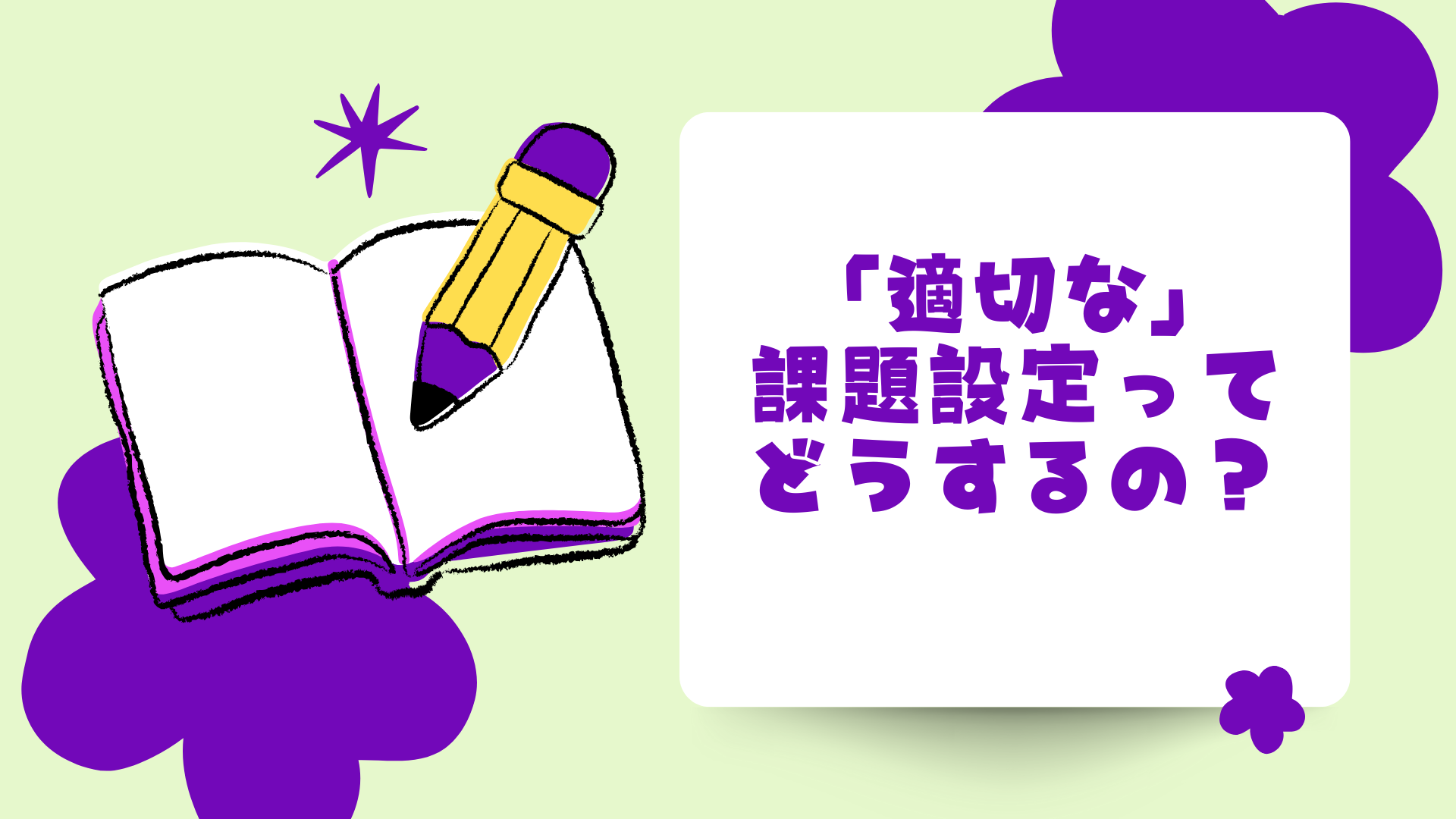
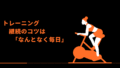
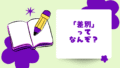
コメント